Breadcrumb navigation
連載コラム ある変革実践リーダーの荒波奮戦航海記 ~海図のない海をすすむ~
若林 健一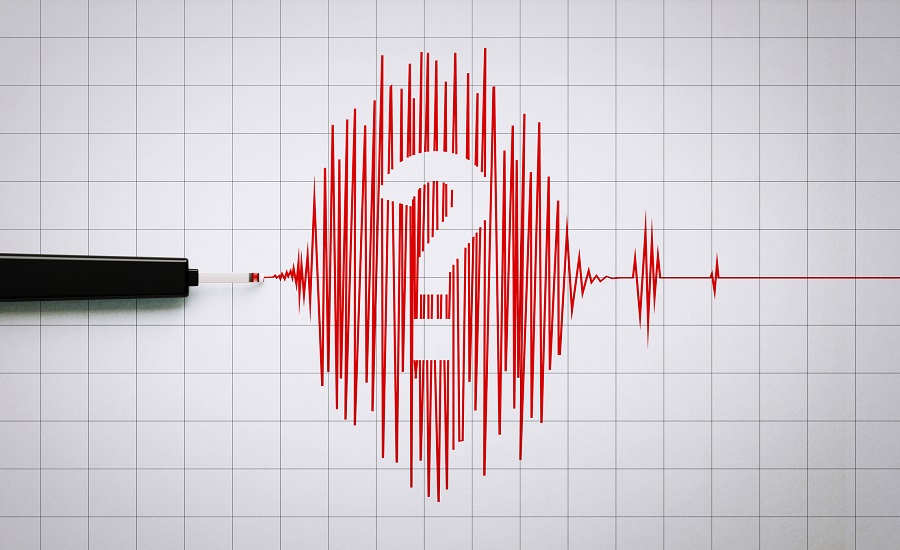
第12回 どん詰まりでみつけた、「他人のものさし」でない世界を生きるとは?
自分のものさしの創り方。「問いを立てる力」とは
他人がつくったものさしとは、既存のものさしとも言える。
AIはデータを与えれば最適な解を出す。データの質、量ともに充実していればAIが人間以上の能力を発揮する場合も多々ある。つまり既存のものさしの中で、最適化するのはAIの得意領域なのだ。
しかし当たり前だがAIには意思がないため、目的は創り出せない。それ故、何をやりたいかを決めるのが人間の大きな役目になる。
「何をやりたいか」とはビジネス観点で言うと、ものさしを自ら創り「問いを立てる力」だ。そしてこの部分こそAIによる価値づくりの源泉であるというのが私の見解だ。
「問いを立てる」ことは、一見簡単そうにみえて実は意外に難しい。なぜなら、私たちは幼少時代からずっと与えられた問いを、いかに早く、いかに正確に解くかということで評価されてきたからだ。
過去問題で傾向と対策を勉強するといったスタイルでは「問いを立てる力」は磨かれない。誰に聞いても答えは持っていない。自分の頭で考え、行動するしかない。

特に昨今のようなテクノロジーの進化が早い時代においては「問いを立てる力」は「何が出来るのか」に大きく影響を受ける。スマホのようなテクノロジーが登場する前と後ではやりたいことに違いが出る。現在であればスマホを使って「こういうことやりたい」と思うのが自然だろう。
また新しいテクノロジーの出現により、従来のプロセスが根本から覆ることさえある。それ故、絶えず「何が出来るか」をウォッチしていなければ、「問い」にズレが生じてしまうのだ。
そして「何をすべきか」と言う観点も忘れてはならない。顧客の声だけを鵜呑みにしては真の顧客価値は産み出せない。社会の動きと連動した問いを立てなければ、目の前にいる顧客に対しての個別最適に走るリスクが発生するからだ。
社会全体で見た時に全体最適にならなければ、結果として顧客の事業も成長出来ない。それ故、顧客の先にいる社会に目を向け、顧客の事業成長を通じて、社会をより良い方向に導いていくという発想が重要だと私は考えている。
AIで価値を産み出すには、様々な知見を掛け合わせて物事を見る力が重要だ。掛け合わせにより引き出しを増やすことが「問いを立てる力」のレベルを上げる。「良質な問いを立て続けられる」チームであること。これが私の目指す姿であり、そのために私たちは日々研鑽に励んでいる。
| 執筆者プロフィール |
|---|
|
若林 健一
NECマネジメントパートナー株式会社 業務改革推進本部所属 1980年 生まれ 2002年 NEC入社 2018年 NECマネジメントパートナーにて高度化サービス開発チームを設立 経営管理・人事・マーケティングを中心に、データアナリティクスとAIを活用した NECグループの経営高度化について、2年間で200プロジェクト実施 NEC Contributors of the Year2019など数々の賞を受賞  |