Breadcrumb navigation
連載コラム ある変革実践リーダーの荒波奮戦航海記 ~海図のない海をすすむ~
若林 健一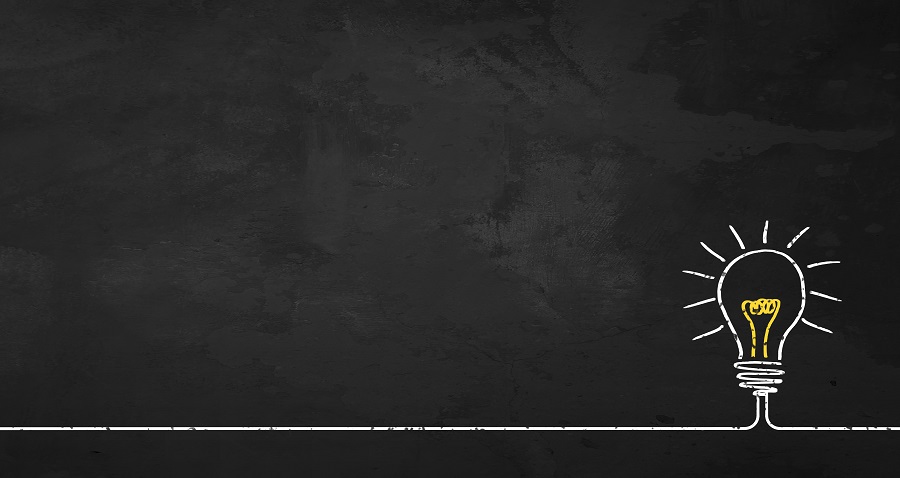
第7回 アイディアだけでは価値をつくれない。実行力を磨く3つのポイント
アイディアで終わらせない
「失敗を恐れずにチャレンジすること。ヒットにすることにこだわること。この両立を目指してほしい。」
チーム設立に際して中西がメンバーに送ったメッセージだ。
一見矛盾しているようだが、この二つは対立した概念ではない。失敗を恐れずチャレンジする一方で、愚直にカタチにすることにもこだわる。変化の激しい時代において、この二つをあわせ持たなければ、真の意味で新しい価値をうむことは出来ない、ということだ。
設立当初、「仕事を創ることが仕事」であった私たちは、最初の2か月間、徹底的にサービスのアイディア出しを行った。お客さまを足繁く訪問し、ニーズを拾い上げ、サービスの仮説を創り出し、検証する毎日。
いくら頭でよいアイディアが浮かんでも、それをカタチにする段階で頓挫するケースも数多く経験した。データを持っているのは誰か、使用するには誰の許可をもらえばよいか、関係者をどのように巻き込めばよいか…、超えるべきハードルは山積み。これらをひとつずつクリアしていくことで、はじめて道がひらけてくる。
「AI」というと最先端で、華やかなイメージを持つかもしれない。しかし実際は、こういった人間臭いアプローチなしに、プロジェクトが成功することはない。
つまり、アイディアそのものに価値があるのではなく、それをカタチにする実行力を伴ってこそ価値がうまれてくるのだ。
実行力を磨け!
それではどのように実行力を磨いていったのか。
私が当時意識していた3つのポイントをご紹介したいと思う。
ポイント1.走りながら考える
新規事業の場合、計画どおりに進むことはまれである。計画を綿密に立てるよりも、自分の立てた仮説をプロトタイピングし、顧客にぶつけ、フィードバックをもらうといったサイクルを高速に回す方が有効だ。
「考えてから走る」のではなく「走りながら考える」のである。
こういう話をすると、場当たり的な行動のように思われてしまうかもしれないが、そうではない。仮説検証で得られた数々のフィードバックを元に、思考をらせん階段状に高めていくのである。
走りながら、考えて、考えて、考え尽くすのだ。
ポイント2.自ら覚悟を持つ
中西が権限を委譲してくれたこともあり、私はたいていの意思決定を自分で行っていた。
他人に意思決定を委ねると、言い訳要因がうまれやすく、自分に甘えが出てしまうと思ったからだ。
自ら意思決定していないと、上手くいかなかった時に、どうしても「あの人の判断が間違っていた」とか「自分だったらこうしていた」という思考に陥りがちだ。一方、自ら意思決定すると、結果に対しての責任が発生し、覚悟がうまれてくる。その結果、真の意味で自らへのフィードバックが機能し、改善サイクルが回せるようになる。
つまり「覚悟」とそれを裏で支える「権限移譲」こそ、実行力のエンジンなのだ。
歴史上、やらされ感のある仕事によって世界を変えた人を、私は知らない。
ポイント3.慣性の法則を利用する
新規性の高い仕事の場合、周囲からの賛同を得られないことはよくある話だ。そうした場合、そのまま正面突破を試みるのは得策でない。実績も上がっていない状態で「いいね」をもらうのが困難な相手に労力をさくのは、両者にとって時間の浪費につながってしまう。
ではどうすればよいか?
(前回のコラム)