Displaying present location in the site.
「ウィル」をマネジメントする
PJ活動お役立ちコラム
第124回 2023年4月11日
「ウィル」をマネジメントする
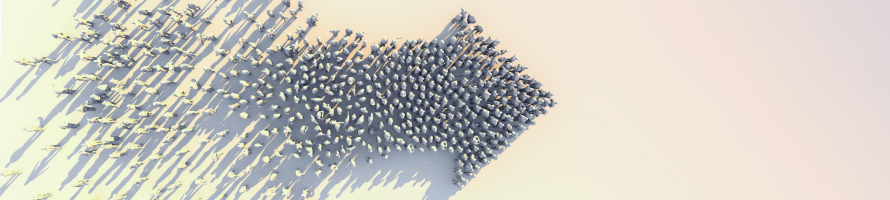
職業柄、筆者の周りは3文字略語やカタカナ言葉にあふれており、そういった表現を使うのはなるべく避けているのですが、どうしても他の言葉に置き換えられないケースがときどきあります。本稿のテーマとしたい「ウィル」もその一つです。
「ウィル」について考える
ウィル(will)は辞書的には「意思」とか「意欲」を指す言葉ですが、プロジェクトにおいて「ウィルを持つ」という言葉を使う場合は、ある目標に対して強い意志や決意を持って突き進む「熱量」が込められていると感じます。実際、活力あるプロジェクトには、たいてい、強いウィルを持ったプロマネないしリーダーが存在しますし、リーダーのウィルの強さはプロジェクト成功の要因のひとつであることは間違いないと思っています。
ところで、ウィルを持つのは一人のリーダーばかりではありません。以下では、プロジェクトメンバーの「ウィル」という観点から、プロジェクトのマネジメントを考えてみたいと思います。
メンバーがウィルを発揮するために必要なこと
プロジェクトメンバーひとりひとりが「ウィル」を持ち、それを発揮してもらうためには、以下のような働きかけが必要です。
-
リーダーのビジョンに共感してもらうこと
メンバーのウィルを喚起するには、まずプロジェクトのビジョンに共感してもらう必要があります。うまくいっているプロジェクトでは、プロジェクト初期の段階でリーダー自身の言葉でプロジェクトの目的やゴール、もっと言えば自分自身のウィル・熱量をメンバーに語り掛け議論する場を設けていたりします。そういった対話を通じて、メンバーの側もビジョンに無理なく共感することができるのだと思っています。 -
個々人のウィルに寄り添うこと
メンバーごとに、プロジェクト参画の経緯もこれまでの経験も違えば、興味・関心の領域も異なります。プロジェクトに対するウィルの所在も様々です。結局は仕事のアサインの仕方なのかもしれませんが、プロジェクト遂行中に発生する小さな課題やタスクひとつひとつを、各人のウィルに寄り添う形でアサインできれば理想的です。メンバーのモチベーションが向上するだけでなく、チーム全体のウィルを束ねていくことにもつながると思います。 -
チームのウィルをマネジメントすること
とはいえ、メンバーのウィルがバラバラでそれぞれ勝手にウィルを発揮していてはプロジェクトは立ち行きません。メンバーがお互いのウィルを理解しその実現に向けて協力し合うこと、それをチームのウィルとして束ねてベクトルを合わせていくことも重要です。
プロジェクトが始まるとどうしても課題管理、問題管理、進捗管理といったことに目が行きがちですが、とくに長期間に及ぶプロジェクトでは、チームやメンバーの「ウィル」も同様にマネジメントすることをお勧めしたいです。初期に考えていた目的やビジョンに変化はないか、進めてみて判明した事実は何か、それに対してメンバーはどう感じているのか、軌道修正は必要か、検討すべき新しいアイディアは無いか、といった議論を定期的に行うのです。フェーズごとの反省会、振り返り会の場を活用するのも良いです。プロジェクトが長くなるとどうしても「無事に終了させる」ことに気を取られ消極的な姿勢に陥りがちですが、節目節目にウィルを思い起こすことで初期に感じていた意欲や情熱、熱量が蘇り、それがプロジェクトにも活気をもたらすはずです。
さいごに
もちろん、上に挙げたことをプロマネ単独で実行するのは簡単ではありません。プロジェクトのビジョンや背景が複雑だったり、規模の大きなプロジェクトである場合は、なおさらです。リモートワークでコミュニケーションも困難さを増すなか、リーダーのウィルとメンバーのウィルを融合させ、それを実行面から支えることも、PMOの重要な役割なのかもしれないと考えるようになりました。
実際、大きなプロジェクトに参画して現場マネジメントのお手伝いをするなかで、偶発的に、強いウィルに出会うことがあります。そのメンバーが克服しようとしている小さいけれど重大な課題や、プロジェクトの先に見据えている新しい世界への展望について束の間語り合うとき、この「熱」を他メンバーやリーダーに伝えなければという使命感に駆られつつ、これもPMOという仕事の醍醐味の一つだなと密かに考えたりするものです。
読者の皆さんは、どのようなウィルを持ってプロジェクトに取り組まれていますか?
本稿が皆さんのプロジェクト運営のヒントになるようでしたら幸いです。