Displaying present location in the site.
「過程」に着目して生産性向上を考える
PJ活動お役立ちコラム
第106回 2022年12月6日
「過程」に着目して生産性向上を考える
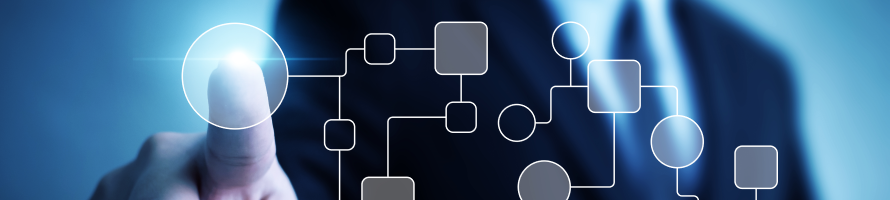
皆さんは、生産性向上ということに悩んだことはありませんか。
生産性、つまりインプット量に対するアウトプット量の多さ少なさは、エンジニアリングの世界ではざっくり言うと単位時間あたりの成果物の量ということになると思います。投入人員あるいは工数に対するソースKL数やバグ数、その消化率、などを計測し、プロジェクト間、作業者間で見比べて分析し、次に役立てる・・・のですが、この議論、どうにも息苦しく感じることはありませんか。
ハイパフォーマー分析にも限界がある
ある組織で、たとえば3%の生産性向上を目指す場合に、生産性が低い人たちに対してある一定の方向性なり方策なりを示して、少しずつ改善を促すことがあります。生産性が高い人=ハイパフォーマーのやり方を可視化して、教育・演習のような形で他メンバーにインプットすることで、全体のパフォーマンスを底上げする、という手法です。我々もプロジェクト改善の一環で、そういったサービスを実際に行うこともあります。
ところが、システム開発というのは、つまるところクリエイティブな仕事です。正確に同じことを繰り返すことでパフォーマンスが向上する製造ラインのようなわけにはいかず、一人一人の経験・知見に依るところがどうしても大きいと感じます。エンジアリングの世界では、ハイパフォーマー分析のような手法による改善は限界がありそうです。実は、エンジニア以外でも同じような状況があるのかもしれず、それが冒頭の「息苦しさ」の背景にあるように思います。
他人とではなく自分と比べる
生産性向上ということについて、長年考えていることがあります。それは、一律の方法論による必要はないのではないかということ。
方法はどうであれ、一人一人が、昨日よりも今日、先週よりも今週、去年よりも今年、3%ずつパフォーマンスを向上させたら、全体としても3%向上するわけです。ハイパフォーマー=他人を見てヒントを得ることはできるかもしれませんが、突き詰めると、比べる相手は自分自身なのです。
そう考えていた折、テレビで興味深いニュースを目にしました。
小学校の体育の授業で、ウェアラブル端末を導入したそうです。持久走の授業では、生徒一人一人の心拍数を端末から取得してモニターに表示、適切な心拍数(70~80)を維持しながら一定時間走り続けることを課します。生徒はそれぞれに工夫をして自分のペースを見つけます。昔のように同じ距離を一斉に走ってタイムを競うということもせず、無理なく走り続けることを身に付けさせる。それが体力向上にもつながるし、また、体育を通じてスポーツに親しんでもらうという本来的な目的にも寄与するということでした。
ここで注目したいのは、他人との比較ではないことと、自分の意思で少しずつ向上させようという力が働くことです。
ニュースの主旨とは明らかに外れるのですが、恐らくこの小学校のそのクラスは、クラス全体の持久走のタイムが向上したはずです。どの生徒も取り組み前に比べて持久力が向上しているはずなので、以前より少し早いペースで走れるようになったことでしょう。自分自身と向き合う中で、いつの間にか「力」が付いていたというわけです。
結果ではなく「過程」に注目する
このことは、組織の生産性向上を考えるうえでも、ヒントになりそうです。
各人が各人なりに自分の仕事のやり方を点検し、課題を見つけ、自らの意思で改善を行う。その積み重ねで組織全体のパフォーマンスがいつの間にか向上するというわけです。とはいえ、どうやって「自分の仕事のやり方を点検」したり「課題」を見つければ良いのでしょうか。
実は、先の体育の授業では、生徒たちに装着させたウェアラブル端末から得られるデータが、生徒自身が自らの課題を発見するためのキーになりました。タイムではなく、心拍数というところがミソです。結果ではなく過程のデータ(フローデータ)なのです。
結果というのは、外部要因や突発要因など様々なことに左右されるものであり、また持久走のタイムのようなものだと先天的な能力の違いにも左右されてしまいますが、過程は、自分の意思だけである程度工夫できる余地があります。
仕事で言えば、「自分の仕事のやり方」です。
従来、「過程」のデータを捉える方法はなかなか無かったのですが、近年は少しずつソリューションが充実してきています。
日常業務においても、TeamsやSLACK等のチャットログや、Officeソフトの更新記録、近年導入が進むPCログ採取ツールに記録されたPC操作ログなど、様々な形で、各人の行動記録=「過程」のデータを取れる環境が整いつつあります。まだもう少し整備されていない感はありますが、自分の意思で課題を発見し、工夫して改善できる土壌ができつつあるわけです。
生産性向上のためとはいえ、他人と比べられるのはやはり気分が良くないものです。
皆さんの職場でも、こういった「過程」のデータを活用し、自分の意思で改善を積み重ねて行くような施策を取り入れてみませんか。
今回のコラムが、皆さんの活動に少しでもお役に立てましたら幸いです。